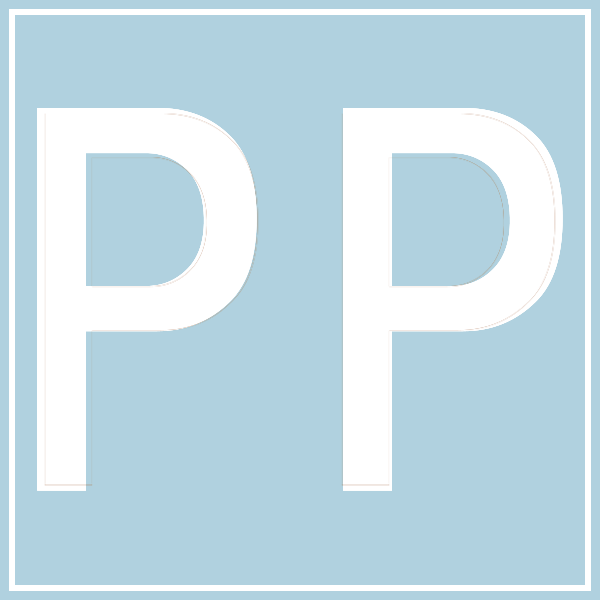●フローラS
フローラSは、みなさんもご存知のオークストライアル。このレースは桜花賞から中1週で行われるため、桜花賞組の参戦はほどんどありません。このためレベルが低い年もありますが、3年前の優勝馬モズカッチャン(次走オークス・2着)のように、遅れてデビューした大物が出現することもあります。
2016年のオークス2着馬チェッキーノも、2013年オークス3着馬デニムアンドルビーも、2010年に史上初のオークス同着を決めたサンテミリオンも、このレースの優勝馬です。今年の桜花賞はレベルが高かったものの道悪で消耗度が高く、上位馬は次走・オークスで余力を残しづらいレースとなっただけに、前記の馬たちのようなキャリア4戦以内の連続連対馬が勝てば、本番に繋がる可能性もあるでしょう。
また、フローラSのペース傾向は、いたってワンパターン。天皇賞(秋)と同じストレートが長い東京芝2000m戦は、本来、緩みないペースが発生しがちですが、フローラSはまだ体力のない3歳牝馬同士の対決。しばしばスローペースが発生し、前からの押し切りが決まっています。実際に過去10年を見ても、良馬場(高速馬場)で行われた年でハイペースになったことは一度もありません。(緩みの少ない流れとなった2016年度は良馬場発表も、午前中に雨の影響あり)
また、過去10年で1番人気を裏切った馬の5頭中4頭は、4コーナー9番手以下だった馬。該当馬は2017年ホウオウパヒューム、2016年ビッシュ、2014年マジックタイム、2011年ダンスファンタジア(ただし、この時は道悪で消耗戦)で、遡れば2009年ミクロコスモスもそうです。
もちろん、良馬場でも3コーナー9番手以下らかでも届く場合もありますが、その場合は2014年のサングレアルや昨年のヴィクトーリアのように内枠を利して終始内々でロスなくレースを運び、4コーナーで外目に持ち出すような乗り方でないと勝ち負けするのは容易ではないでしょう。確かに、一昨年のこのレースでは、サトノワルキューレの大外一気が決まりましたが、よほどの瞬発力の持ち主でないと厳しいものがあります。
今年の東京芝コースは例年ほどの超高速馬場ではありませんが、千両賞を逃げ切り勝ちしシャンドフルールが内枠を利しての逃げ。これに外からセントポーリア賞で2番手から勝利したショウナンハレルヤが内に切り込みながら、ここも2番手を狙って来るかというメンバー構成。ウインマリリンやスカイグルーヴなどの先行馬も出走しており、ある程度はレースが流れる可能性が高いですか、それでも平均ペースくらいで収まる公算大。そこを考えると、やはりある程度は前の位置を取れる馬を本命にするのがベストで、前か後ろかを問われれば、やはり前に行ける脚のある馬が優勢でしょう。
●マイラーズC
安田記念のステップレースの位置付けとなるマイラーズC。このレースは4月の阪神最終週から、4月の京都開幕週に舞台を移して、今年で9年目。しかし、京都に移してから、このレースの優勝馬で安田記念を制した馬は皆無。昨年のインティチャンプは、このレースをステップに安田記念を優勝していますが、同馬はこのレースで4着に敗れており、また、一昨年の2着馬モズアスコットも、マイラーズC・2着後に、オープンの安土城Sを叩いての安田記念終出走でした。
これは、なぜか? 良馬場ならば走破タイム1分32秒台は当然、1分31秒台でも平気で出るほどの超高速馬場で、スピードばかりが求められるからでしょう。前哨戦は無理をさせないことも大切ですが、「負荷」も求められます。つまり、心肺機能(スタミナ)の強化です。しかし、マイラーズCではスタミナを補えないのだから、本気で安田記念を勝ちたいのであれば、ここをステップにして勝ち負けするのはタブーでしょう。
それだけスピードが問われるレースだからこそ、コーナーロスは致命的。3年前のイスラボニータとエアスピネルの勝敗を分けたのも、終始インにこだわて騎乗したイスラボニータ&ルメール騎手と、外から来られて外に出しながらの競馬になったエアスピネル&武豊騎手の差。また、一昨年のこのレースを制したサングレイザーは、終始中団の内々でレースを進めて、直線で外に持ち出した福永騎手の完璧騎乗によるものでもありました。
今年の京都芝コースは、前開催が異常に時計を要していたこともあり、例年のような超高速馬場ではありません。京都芝1600mは最初の3コーナーまでの距離が715mと長く、逃げ、先行馬が集うとある程度ペースが上がりますが、今回の実績馬は前走で差し、追い込み競馬をした馬ばかり。逃げ、先行馬が手薄なだけにスローペースが濃厚でしょう。
また、今回で一番の実績馬は昨年の春秋のマイルG1を制したインディチャンプですが、昨春のこのレースや、昨春の毎日王冠のように、叩き台に徹してくるのか? いかにも叩き台の仕上げではありますが…同馬がぶっ飛ぶとなるといくらでも波乱の可能性がありそうです。