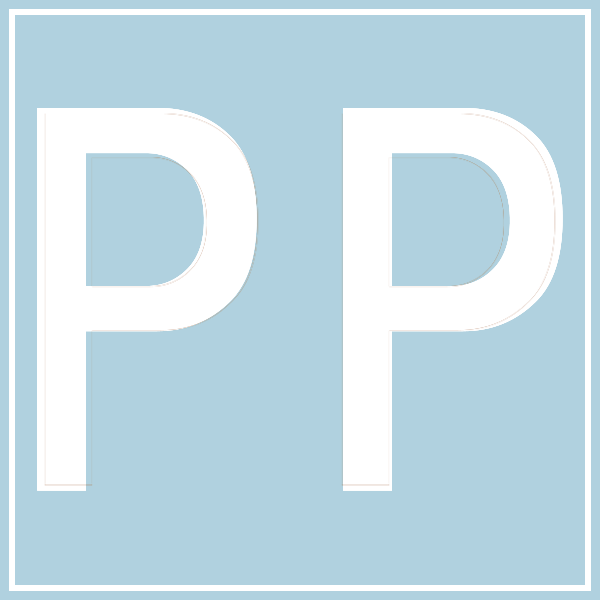シンザン記念は、過去10年の優勝馬からジェンティルドンナ、ミッキーアイル、アーモンドアイとG1馬を3頭も輩出したレース。また、2016年は2着のジュエラー、2017年は3着のペルシアンナイト、6着のアルアインがその年のG1を制しており、ひと足遅れて大物が出現することもあります。
みなさんもご存知のように、昨年暮れの朝日杯フーチュリティS、ホープフルSともにハイレベルでした。その上でシンザン記念でもコントレイル、サリオスに匹敵する、もしくはそれ以上の大物が誕生するのか? 特にコントレイルは、東京スポーツ杯2歳Sで古馬通用レベルの指数をマークしているだけに、それを上回る大物となると決して簡単なことではありません。しかし、なかなかの素質馬が揃ったことも事実です。
また、この時期の3歳重賞も成長合戦で、レベルの高いレースほど前走で敗因なく、あまりに負け過ぎている馬は巻き返せません。それだけに近走の勢いを示すPP指数の「能力値」は重要。ただし、昨年の朝日杯フーチュリティSは逃げ、は先行馬に厳しい流れ。つまり、タガノビューティーの前走4着時の0.6秒差(4着)時の指数は展開に恵まれたものです。
同馬の前走は、初芝でのパフォーマンスとしては褒められますし、ダートのプラタナス賞を断然の末脚「34秒8」て完勝した点も褒められます。しかし、展開に恵まれて好走した馬、特に差し馬というのは、前走からの大きな上積みが期待できません。それだけに正攻法の競馬で順当な上昇を見せている馬を本命視するのが上策でしょう。
また、新馬戦をあまりに高い指数で圧勝した馬も、先週の福寿草特別で1番人気に支持されたレッドフラヴィアのようにドボンする場合もあります。もちろん、順当に勝ち上がる場合も少なくないのですが、デビュー戦からその馬の素質を上回るような消耗度の高いレースを差せた場合には、ダメージが出て取りこぼす場合もあります。さて、ルーツドールは、レッドフラヴィアなのか? 大物なのか? このジャッジメントもこのレースの大きなポイントになるでしょう。
最後にシンザン記念の展開。このレースの舞台、京都芝外回り1600mは、スタートしてから最初の3コーナーまで約712mも距離があります。しかし、前半2F目を過ぎてから徐々に坂を上って行くため、逃げ、先行馬が序盤で行き切っても坂で減速する形。騎手が坂を目標に動いて行くため、平均ペースになりやすいのが特徴。
しかし、古馬の上級条件は平均ペースでも下級条件や3歳戦だと、速く動き過ぎることもあるため、ややハイペースになることもあります。また、騎手の意識としても、3歳になると逃げ馬をある程度行かせる意識が働くのも要因でしょう。今年はダートの逃げ馬ディモールトがどうでるかはわかりませんが、逃げ馬コルテジアを始め、前に行きたい馬がそれなりに揃った一戦。平均ペースかそれよりもやや速くなることも視野に入れて、予想を組み立てたいです。