実は中野騎手には、日本人初のコロナ感染騎手になっていたかも〜なエピソードがありました…Σ(・ω・ノ)ノ!
4月8日発売の競馬王5月号『波乱万丈!中野省吾奮闘記~着地点を探して~』では、中野騎手が謎な四つん這い生活をする意味と近い将来の目標を掲載しています。
中野騎手、最近ふつーの人になったような気がしてましたが、やはり変人でした(;’∀’)
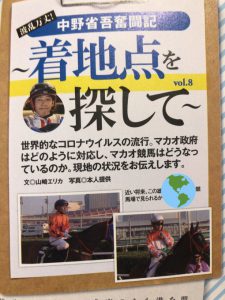
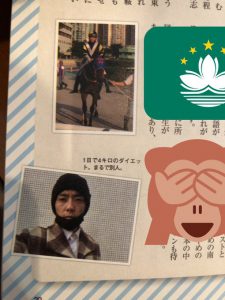
実は中野騎手には、日本人初のコロナ感染騎手になっていたかも〜なエピソードがありました…Σ(・ω・ノ)ノ!
4月8日発売の競馬王5月号『波乱万丈!中野省吾奮闘記~着地点を探して~』では、中野騎手が謎な四つん這い生活をする意味と近い将来の目標を掲載しています。
中野騎手、最近ふつーの人になったような気がしてましたが、やはり変人でした(;’∀’)
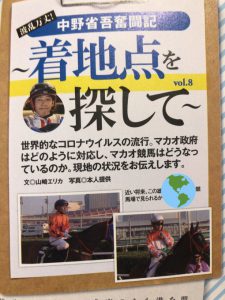
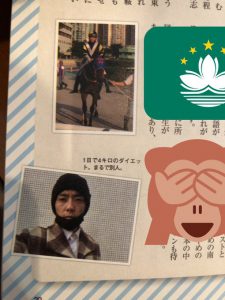
今年のトゥインクルナイター開幕後、最初のダートグレードとなる東京スプリント。このレースはダートグレードとしては歴史が浅く、今回で12回目。かつて4月に行われていたJRAのプロキオンS(阪神ダ1400m)が夏場へ移行し、3月の黒船賞から5月のかきつばた記念まで短距離のダートグレードがなかったことから、3月に行われていた東京シティ盃が「東京スプリント」と名を改め、この時期に施行されるようになりました。
4月に行われる短距離のダートグレードはここだけ。そのうえダ1200m戦は前年のカペラS以来となり、この先も6月の北海道スプリントカップまで番組がありません。このため前年のG1・JBCスプリントがダ1200mで行われた年は特に、JBCスプリントの上位馬をはじめとする、ダ1400mよりもダ1200mでこそのトップスプリンターが集います。しかし、2017年のニシケンモノノフのように、前年のJBCスプリントの優勝馬でありながら、その後に順調さを欠いて通用しない場合もあります。
それでもやっぱり実績は重要……
続きはこちら!
https://umanity.jp/racedata/columndet_view.php?cid=12268
予想はこちら!
https://nar.umanity.jp/coliseum/coliseum_view.php?user_id=3100000007&race_id=2020040820010311
大阪杯はG1に昇格して今年で4年目。かつてのこのレースは天皇賞(春)の前哨戦のひとつでしたが、G1になって賞金は約2倍。天皇賞(春)では距離が長いという馬には、当然、ここが本番になります。しかし、ここから始動する馬は、さすがにここが本番ではないでしょう。
2017年のキタサンブラックは、前年のG1で2勝、2着1回、3着1回と実績断然、能力が抜きん出ていたので始動戦でも優勝しましたが、それでもそれまでG1・未勝利、前年の天皇賞(秋)の3着が最高というステファノスに0.1秒差まで詰め寄られました。キタサンブラックとしては凡走のPP指数で1着。つまり、ここから始動するワグネリアンはここが本番ではないということです。
ただし、今年は1番人気のダノンキングリーを始め、始動戦の前走でPP指数の最高値をマークした馬、それに準ずる指数をマークした馬が多数。休養明け好走後で好走した反動が出て、前走比で指数を下げても不思議ない状況下です。今回でどの馬が上積みがあるのか(?)を読むのが焦点となってくるでしょう。
また、大阪杯が行われる阪神芝2000mは、スタートしてから最初の1コーナーまでの距離は約325mと短いため、内枠有利の傾向。特に大阪杯は先週までAコース→今週Bコースに替わるため、なおさら内枠が有利になります。
実際に大阪杯がG1に昇格された2017年も2番枠のキタサンブラックと4番枠のステファノスのワン、ツー決着でした。また、2018年も大外15番枠から向こう上面で一気に先頭に立ち、内々と通ったスワーヴリチャードが優勝。2~3着馬も内目の枠から内々を追走した馬でした。また、昨年も前年の有馬記念の覇者ブラストワンピースが外目の枠から3~4コーナーの外を回して1番人気を裏切り、3番枠のアルアインが優勝。2番枠のワグネリアンが最短距離を追走して、長期休養明けながら3着と好走しています。
さらに阪神芝2000mは、スタート直後に上り坂があるため、あまりペースが速くならないのがポイント。特に近2年は逃げ馬不在だったこともあり、超絶スローペース。逃げ馬不在で先行馬に武豊騎手、ルメール騎手など、目標となる騎手がいなかった一昨年は、5F通過が61秒1の異常なスローペースで3コーナーに当たる5F目から一気にペースが上がり、ラスト4F目から1ハロン11秒台前半のロングスパート戦になりました。スローペースになるほど、3コーナー地点で前と内がより有利の決着になります。
さて、今年はどうかと言うと、ジナンボーが逃げる展開ならスローペースが濃厚でしょう。しかし、今回はロードマイウェイが最内枠に入り、スタートが上手い武豊騎手に乗り替わったことで、ハナを主張する可能性もあります。いや、こちらの可能性が高いかもしれません。武豊騎手は競られることを嫌ってスローペースで逃げることを嫌う騎手だけに、ロードマイウェイが逃げるとするならば、平均ペースまで上がるでしょう。今回はどちらが逃げても対応できる形で予想を組み立てたいです。
ダービー卿チャレンジTは、ハンデ戦ながら、この先のマイラーズCや京王杯スプリングC、さらには安田記念へと繋がる一戦。このレースの優勝馬には、ショウワモダン(2010年)、トウケイヘイロー(2013年)、モーリス(2015年)のように、同年の安田記念や秋のG1戦線で活躍している馬もいます。上がり馬が勝てば、この先のG1レースが見えてくる場合もあります。
また、2010年にショウワモダン(2番手)とマイネルファルケ(1番手)と行った、行ったが決まっているように、中山芝1600m重賞としては珍しいほど、スローペースとなることがあります。先週Aコース→Bコースに替わることで、前週よりも馬場が高速化することが多いからでしょう。騎手は前週の感覚でレースをすることが多いので、結果、逃げ、先行馬を残らせてしまっているのです。
しかも、前回の火曜日の開催が雪の影響で稍重発表以上にタフな馬場でしたから、良馬場の今回は少なからずとも高速化するはず。それだけに前に行く馬は警戒したほうがいいでしょう。
また、秋の中山開幕週で超絶~超高速馬場で行われることが多い、京成杯オータムHほど顕著ではありませんが、インコースを通れる内枠の馬が活躍しているのも事実。2017年に優勝した3番枠のロジチャリスを始め、過去10年で4番人気以下で優勝した馬は、全て内枠か内々を通した馬でした。この辺りは、最初のコーナーで内に入れられないと、終始外々を回らされてしまうことになる円状コースの中山芝1600mの傾向どおりと言えます。
今回は逃げなければ持ち味が生きないトーラスジェミニに、逃げるとしぶとい大外のマイスタイル、2列目狙いのボンセリヴィーソ、前走から2Fの距離延長と1番枠で前に行く可能性が高いナインテイルズ、クルーガーと逃げ、先行馬が集いました。2番枠のストーミーシーも前走の東風S同様に、スタートを決められれば前に行くでしょう。
さすがにある程度はペースが上がると見ています。しかし、全体的な傾向としてBコースに替わることで、厚程度ペースが速くなっても前からの押し切りが決まっているだけに、前に行く馬を侮り過ぎないほうがいいでしょう。
船橋で行われるマリーンカップは、数ある牝馬限定ダートグレードの中でもっとも本命党好みのレースです。もともと船橋競馬場は、直線が長い上にスパイラルカーブが使用されており、後続馬でもトップスピードに乗せたまま3~4コーナーを回ることが可能。内ががっぽり開いてイン突きが決まることがほとんどなく、騎手の手腕が問われにくいコース。このため1番人気の勝率、複勝率がもっとも高い競馬場となっています。
続きはこちら!
https://umanity.jp/racedata/columndet_view.php?cid=12257
予想はこちら!
https://nar.umanity.jp/coliseum/coliseum_view.php?user_id=3100000007&race_id=2020040219010211
マ―チSには「1番人気は勝てない」というジンクスがあります。2009年に1番人気に支持されたエルポワールシチーこそ9年ぶりに優勝しましたが、それ以降は全く勝てていません。連対したのも2016年に1番人気に支持されたバスタータイプだけ。
昨年は、前々走のボルックスSで逃げて4馬身差の圧勝したテイオーエナジーが1番人気に支持されましたが、2列目のインから直線で明確に詰まって位置を下げ、10着に敗れました。一見、アンビリバボーな敗戦のようですが…前走の佐賀記念ではハイペースで逃げたことを考慮しても大敗の3着だったあたりから、調子落ちしていた感があります。馬の手応えがひと息だったから、逃げすに2列目のインを狙い、道中で外に出せるタイミングがあってもスルーしたのでしょう。
このようにマーチSはハンデ重賞ということもあって、ここが目標ではなく流動的に出走してくることがほとんどです。「それほど調子良くないけど、相手もそんなに強くないから使ってみるか…」、「ハンデが軽いから、とりあえず出走」、「実績馬でハンデ重いけど、負けてもハンデのせいにできるから、まっ、いいかぁ~」という具合です。
あのエルポワールシチーでさえも、同年の平安S・2着、フェブラリーS・4着の実績馬でありながら、そこまで速いラップを刻んだわけでもないのに、ラスト1Fで急失速。ダイショウジェット、サトノコクオー、トーセンアーチャーなどに0.2秒差まで追い詰められるギリギリセーフの勝ち方でした。これも前走のフェブラリーSが大目標だったことと、トップハンデ57.5㎏が影響したのでしょう。さて、今年の1番人気はどの馬か?
また、このレースが日曜日に行われていれば不良発表で高速ダートは確定的でしたが、火曜日となれば回復してくることでしょう。現時点では重発表ですが、マーチSの頃には稍重、場合によっては良まで回復するのではないのでしょうか。中山の場合、そもそも時計が掛かるので、稍重発表でも他場の良くらいまで時計を要します。少なくとも日曜日ほど前に行ける馬が楽ではないので、そこも考慮して予想を組み立てたほうがいいでしょう。
●毎日杯
かつての毎日杯は、NHKマイルCの前哨戦の意味合いを持ち、2008年のディープスカイ、2010年のダノンシャンティなどが、このレースを制して、NHKマイルCも制しました。しかし、近年は多様化。2013年のキズナや2016年のスマートオーディンのように、ここから京都新聞杯、そして日本ダービーを目指す馬もいれば、2017年のアルアインのように、ここから皐月賞を目指す馬もいます。要は、この先の何かしらのG1を目指すための、賞金加算のレースです。
しかし、1つだけ共通して言えるのは、過去10年の連対馬20頭中18頭がキャリア2~5戦目以内の馬ということ。キャリア5戦以上で優勝したのは、2011年のレッドディヴィスのみ。しかし、同馬にはシンザン記念勝ちの実績がありました。キャリア5戦目以上の馬は大きな上昇は見込めないだけに、それまでに実績がないと厳しいということなのでしょう。
一方、キャリアが1戦で2着と好走したのは昨年のウーリリで、前年11月の京都芝1800mの新馬戦を、好指数「-3」(新馬戦としてはかなり優秀)で勝利していた馬でした。新馬戦で高い素質を見せ、休養中にさらに成長したことで、ここでもいきなり通用したのでしょう。キャリア1戦馬を狙うのであれば、新馬戦で好指数をマークした、いわゆる素質の高いタイプに限定されます。
また、毎日杯が行われる阪神芝外1800mは、Uターンコース。スタートして最初の3コーナーまで約665mもあるために、逃げたい馬が集うと隊列争いが激しくなり、オーバーペースが発生することもあります。しかし、逃げ馬不在や、逃げ馬が1頭の場合はそこまでペースが上がりません。昨年のランスオブプラーナのように、マイペースで逃げ切ることもあります。
ただし、そこまでペースが上がらなくても、最後の約600m~ゴール手前の約200mまでが下り坂のコースだけに、その下りで勢いに乗せて、ラスト1Fの急坂を楽に上がれる差し、追い込み馬のほうが有利でしょう。実際にこのレースでは、キズナやスマートオーディンが追い込みで勝利しており、逃げて3着以内の馬がランスオブプラーナ1頭に対して、追い込みは1着2回、2着2回、3着3回の好成績。逃げと追い込み馬の3着以内を比較すると、断然に追い込み馬のほうが活躍していることから、このレースでは後半型の馬を中心視するのが好ましいでしょう。
●日経賞
日経賞は先週の阪神大賞典同様に天皇賞(春)の前哨戦。2008年のマイネルキッツ、2013-2014年のフェノーメノがここをステップに天皇賞(春)を制しているものの、ここ4年間は本番での3着以内はゼロと、重要性が薄らいでいます。これは3年前より大阪杯がG1に昇格され、ステイヤーは阪神大賞典とステップに、キタサンブラックのような実績馬は大阪杯から始動するケースが増えたからでしょう。
また、日経賞は有馬記念と同じアップダウンの激しい中山芝2500mで行われるため、しばしばスローペースが発生します。しかし、同じスローペースでも下級条件は、シンプルな上がり勝負(末脚比べ)になることが多いのに対して、上級条件は中山の短い直線を考慮して仕掛けのタイミングが早くなる傾向があります。実際にこのレースの過去10年を見ても、上がり勝負となったのは、小頭数9頭立てでゴールドアクターとサウンズオブアースがハナを譲りあった2016年くらいです。
2014年の優勝馬ウインバリアシオンのように、追い込み馬は向こう正面の下り坂である程度勢いに乗せて、3~4コーナーの外から位置を押し上げてくる傾向があり、逃げ、先行馬もそれを意識して早めに動いているケースが多く、結局、持久力も問われてるレースになっています。つまり、長距離適性に疑問がある馬が通用していないことがほとんどということです。
また、2017年のこのレースで前年の有馬記念の3着馬ゴールドアクター(1番人気)や前年の菊花賞の2着馬レインボーライン(2番人気)が馬群に沈み、2018年にも菊花賞馬キセキ(1番人気)や前年の阪神大賞典3着&京都記念2着トーセンバジル(2番人気)が、見事に馬群に沈んだように、今回が始動戦の馬は苦戦しています。休養明けで不足するのは、スタミナですから、このレースがいかに持久力も問われているかの象徴でもあります。
そもそも前哨戦は、実績馬にとっては叩き台のため、人気に応えられないことがままありますが、先週の阪神大賞典のキセキのように、スタミナが問われるレース、長距離戦ほど凡退率がアップする傾向。それだけに今年も休養明けの実績馬エタリオウよりも、今年レースを使われている馬を中心視するのが好ましいでしょう。
●スプリングステークス
スプリングSは、過去10年で2011年のオルフェーヴル、2013年のロゴタイプ、2015年のキタサンブラック、2017年のエポカドーロなど、4頭の皐月賞馬を輩出しているレース。また、昨年はこのレースで7着に敗れて皐月賞出走権を逃したロジャーバローズが、京都新聞杯2着を得て、ダービー馬となりました。
今年は東京スポーツ杯2歳Sを、世代最高指数「-20」で制したコントラチェクや、朝日杯フーチュリティSを次点の指数「-18」で制したサリオスなど、2歳にして古馬オープン級の馬たちが集っているため、それらを上回るパフォーマンスで主役の座を勝ち取るのは至難の技。
しかし、ホープフルSの2着馬ヴェルトライゼンデや上がり馬が集い、戦前の段階の評価としては弥生賞ディープインパクト記念以上のメンバーが集いました。今年の弥生賞は、サトノフラッグがホープフルSの3着馬ワーケアを撃破しているように、終わってみれば意外とハイレベルの指数「-17」でしたが、スプリングSはそれを上回る馬が誕生するのか(?)、今から楽しみでなりません。
また、今開催は中山芝1800mで中山記念、中山牝馬Sが行われ、今週はフラワーC、スプリングSが行われます。先週の中山牝馬Sは大雪の影響で例外的に消耗戦となりましたが、前記4レースを総合的にペースが上がりやすい順にあげると、中山記念、中山牝馬S、スプリングS、フラワーCになります。これについてはフラワーCの傾向でもお伝えしました。
古馬トップクラスが集う中山記念は、ほとんどの馬が2コーナーの急坂の下り(おおよそ3.5~4F目)で減速させないため(序盤が極端なスローペースだと、この地点で勢いに乗せる場合もある)、道悪にでもならない限り、向こう上面で大きくペースが緩むことはほどんどありません。それゆえに最初の1コーナーまでの距離が約205mと短く、前半で急坂を上るコースながら、前が潰れることもしばしばあります。
しかし、まだ体力のない3歳牝馬同士の戦いとなるフラワーCは、騎手が2コーナーの急坂をゆっくり下ることを意識するので、向こう上面でペースが上がらず、昨年度のコントラチェックのように逃げ馬が楽々逃げ切ることもあります。
一方、スプリングSは3歳馬限定戦でも、牝馬よりは体力のある牡馬同士の戦いですから、フラワーCよりはペースが上がります。明確に2コーナーの下り坂でペースが緩み、どスローだったのは、逃げ馬が不在だった2015年のみ(優勝馬キタサンブラック)。それ以外の年はさほど緩まずに、平均ペース前後で決着しています。つまり、フラワーCは逃げ、先行馬が有利ですが、スプリングCは差し馬にも十分チャンスがあるということ。実力どおに決まることが多いです。それだけにここは実力重視で予想を組み立てたいです。
●阪神大賞典
阪神大賞典は、3年前に大阪杯がG1に昇格して以来、天皇賞(春)のステップレースとして一本化。一昨年のこのレースを制したレインボーラインが天皇賞(春)を制したように、近年は特に天皇賞(春)に繋がるレースとなっています。3年前もこのレースで連対したサトノダイヤモンドとシュヴァルグランが、天皇賞(春)でキタサンブラックの2着、3着と活躍しています。
このレースは当然、芝3000m戦だけあって長距離適性が問われます。実際に過去10年の連対馬20頭中9頭に芝3000m以上での実績がありました。該当馬は、2010年の優勝馬トウカイトリック、2011年の2着馬コスモメドウ、2012年の2着馬オルフェーヴル、2013年~2015年まで3連覇したゴールドシップ、2014年の2着馬アドマイヤラクティ、2017年の優勝馬サトノダイヤモンド、2017年の2着馬シュヴァルグラン。
つまり、今年の該当馬は菊花賞馬キセキとユーキャンスマイルということになりますが、この2頭は今回が始動戦。ここでは実力最上位ですが、スタミナが不足する休養明けで芝3000m戦となると、失速する可能性もあります。この実力上位の2頭が本来の力を出し切れなければ、高配当決着の可能性は十分あるでしょう。
最大の穴は、2015年に7番人気で2着と好走したデニムアンドルビーのような芝3000m以上を使われたことがない隠れステイヤーを見つけること。デニムアンドルビーはどのような馬だったかというと、デビューから序盤で置かれて、一度も先行したことがなく、ジャパンCではスローペースをロングスパートで2着と好走している実績馬でした。そう、このいい脚を持続させる、ロングスパートこそがステイヤーの証。そのことも踏まえ予想を組み立てたいです。
★★★★★★★★★★
Twitterもよろしく!
@_yamazaki_erika
★★★★★★★★★★
今開催は中山芝1800mで中山記念、中山牝馬S、フラワーC、スプリングSと4つの重賞が行われます。先週の中山牝馬Sは大雪の影響で例外的に消耗戦となりましたが、前記4レースを総合的にペースが上がりやすい順にあげると、中山記念、中山牝馬S、スプリングS、フラワーCであることは先週の中山牝馬Sの傾向でお伝えしました。
古馬トップクラスが集う中山記念は、ほとんどの馬が2コーナーの急坂の下り(おおよそ3.5~4F目)で減速させないため(序盤が極端なスローペースだと、この地点で勢いに乗せる場合もある)、道悪にでもならない限り、向こう上面で大きくペースが緩むことはほどんどありません。それゆえに最初の1コーナーまでの距離が約205mと短く、前半で急坂を上るコースながら、前が潰れることもしばしばあります。
しかし、まだ体力のない3歳牝馬同士の戦いとなるフラワーCは、騎手が2コーナーの急坂をゆっくり下ることを意識するので、向こう上面でペースが上がらず、しばしば前残りが発生します。実際に過去10年(2011年度は阪神開催)で、昨年度のコントラチェックを始め、2009年のヴィーヴァヴォドカ、2015年のアルビアーノ、2016年のエンジェルフェイスの逃げ切りVが決まっています。
一方、差しが決まったのは、重馬場だった2013年のみ。それ以外は、逃げ馬か、先行馬が優勝しているだけに、今年も前に行ける馬を中心視するのが上策でしょう。
また、このレースは桜花賞に出生権利のない重賞路線馬と2勝馬と、前走で新馬、未勝利戦を勝ち上がったばかりの馬の対戦図式となります。2010年にチューリップ賞で包まれて4着に敗れたオウケンサクラが、このレースで巻き返して優勝したパターンもありますが、そのレベルの馬が出走してこない限りは、牡馬相手の芝1800m以上の2勝クラスを勝利した馬が優勢でしょう。
芝1800m以上の2勝クラスは、クラッシックを見据える強豪が集うレースで、そこを勝つとシンプルに強いと判断できる場合が多いからです。そうなると今回で該当するのは、シーズンズギフトやクリスティ、ショウナンハレルヤといった面々になりますが、今年はそれらが2014年の優勝馬バウンスシャッセ(前走・寒竹賞勝ち)や2016年の優勝馬ファンディーナ(前走・つばき賞勝ち)ほど、指数が断然の存在ではありません。そもそも何が1番人気になるのかしら定かではありませんが、波乱の可能性も十分あるでしょう。
●フィリーズレビュー
フィリーズレビューが行われる阪神芝1400mは、先々週の「阪急杯の傾向」でもお伝えしたように、差し、追い込み馬が有利なコース。スタートしてすぐ最初の3コーナーを向かえる阪神芝1200mよりも最初の直線が1F長く、約443mもあるため、逃げ、先行馬が多く出走しているほど、ポジション争いが激化し、ペースが上がりやすくなります。
実際にこのレースの過去10年、全て平均ペース以上で決着しており、ハイペースが3度、超絶ハイペースが5度も出現。昨年は前走のさざんか賞を逃げて圧勝し、メンバー中NO.1のPP指数をマークしていた指数上の主役イベリスでさえも、このレースでは先行して4着に敗れています。(次走のアーリントンCで巻き返しV)
もっともイベリスが敗れた背景には、同馬は前走の芝1200mで結果を出したこともあり、距離延長を懸念して、逃げなかったのもあるでしょう。実際に前走で芝1200mを使っていた馬というのは、過去10年で29頭出走し、3着以内だった馬はゼロという成績。
これは前走芝1200m組はそのスピードに任せて前に行くか、距離延長を懸念して脚をタメるかというように、立ち回りに制約がついてしまうのが一番の理由でしょう。もちろん、展開にマッチすれば馬券圏内に突入しても不思議ありませんが、レース運びに制約がつくという意味では不利です。
逆に先行策から押し切って優勝した馬は、2012年のアイムユアーズ、2014年のベルカント、2016年のソルベイグなど後々の重賞、特にスプリント戦で活躍した馬ばかり。また、どの馬も前走で距離1400m以上のレースに出走しており、迷いのない位置取りができたことも勝因でしょう。
。
さて、今回は、逃げることで素質が開眼した最内枠のカリオストロがハナを主張する可能性が高いと見ていますが、外からさざんか賞を逃げ切り勝ちしたヴァラークラウンが競りかけていく公算大。フェアレストアやケープゴッドなどの先行馬も出走しているだけに、やはりハイペースが濃厚でしょう。カリオストロやケープゴッドが強いのは重々承知の上で、やっぱり前走で芝14100m以上を使割れている差し馬を中心視したいです。
●金鯱賞
金鯱賞は2017年から大阪杯へのトライアルレースとして生まれ変わり、今年より中京開幕週から2週繰り下げて行われるようになりました。2017年以降、ステファノス、ヤマカツエース、スワーヴリチャード、アルアインがここをステップにして大阪杯で3着以内に好走しているだけに、要注目でしょう。
さて、このレースの傾向はというと、中京芝2000mは前半でゴール前の直線の坂を上って、後半で坂を下るコースのため、前半スローの上がり勝負が発生しやすいコース。しかし、古馬一線級が集うこのレースは、大半の馬が3コーナーの下り坂で勢いに乗せて動くため、単調な前残りになることは稀。
前に行く馬も3コーナーからもうひと脚使えなければ厳しいものがあり、結局のところ、ある程度持久力も問われていることになります。つまり、前に行ったことにこしたことはなく、差しでも十分届きますが、3~4コーナーで差し馬の外から動かなければならない追い込み馬は苦戦するでしょう。
実際にこのレースが芝2000mで行われるようになった過去8年を見ても、追い込み馬の3着以内は一度もありません。この傾向は2週繰り下がって馬場が悪化したとしても、大きくは変わらないはず。しかも、今回で逃げるのは、まず、ダイワキャグニーですから、なおさらスローペースが濃厚でしょう。つまり、サートゥルナーリアは出遅れ癖いのある馬で、出遅れた場合が怖いのですが…楽に先行なら有力でしょう。